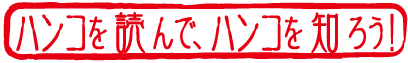
![]()
|
ハンコは、中国の影響で日本へもたらされ、もともと国家や権力者が使う公印(こういん)として、その文書や内容を証明するために使われてきました。そうした権力者が使ったハンコとしては、天皇のハンコや徳川家康(1542〜1616)のハンコが押された文書を紹介します。 |
![]()
|
ハンコは、古くは、文字の書かれた部分全てに押され、書き換えられるのを防ぎました。ハンコには、このように削除や改変を防ぐ意味もあったのです。たとえば、書や絵の右上に押されているハンコは関防印(かんぼういん)といい、書や絵のはじまりを示し、途中で切られるのを防ぎます。一方、署名のあとに押されているハンコは落款印(らっかんいん)といい、文章や絵の終わりを意味し、制作の証明となりました。 |
![]()
|
和歌浦出身の町人で、江戸時代の紀州を代表する文人画家の一人である桑山玉洲(くわやまぎょくしゅう)(1746〜99)の使用したハンコ16個が、約45年ぶりに再発見され、公開されます。そのハンコが押された絵とともに並べて展示し、実際のハンコと押されたハンコを比較しながら見ることができます。 |
![]()
|
紀伊藩10代藩主の徳川治宝(はるとみ)(1771〜1852)のハンコには、役職や位といった肩書きを示したものがあります。たとえば、中納言(ちゅうなごん)は「黄門(こうもん)」、大納言(だいなごん)は「亜相(あそう)」、正二位(しょうにい)は「特進(とくしん)」のように、肩書きが変わるとハンコも変えました。そのため、押されているハンコにより、制作された時期がわかるのです。 |
![]()
|
ハンコは、同じ文字や文様を何度でもくりかえし押せる便利な道具です。ハンコが作者の証明として利用されたのは、文書や書や絵だけではありません。陶磁器(とうじき)のようなやきものでは、焼き上げる前の柔らかい土にハンコを押して、作者の証明とし、また、それが真偽の判断材料にもなりました。 |
![]()
|
ハンコには、持ち主や所蔵者を示すために押される所蔵印(しょぞういん)というものがありました。他人の持ち物と区別したり、盗難を防ぐ目的で押されました。こうしたハンコから、以前の持ち主がわかる場合もあり、歴史的に重要な情報となります。桑山玉洲(くわやまぎょくしゅう)の所蔵印が押された貴重な中国の絵は初公開です。 |